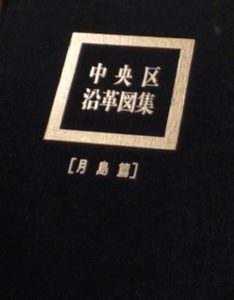Q:最近は月島観音縁日が毎月27日、小さい規模になって寂しい思いがしてますけど、これはいつ頃からやっていたんですか。
あれは、最初のころはどうなんでしょうね。戦後いつごろからかしらね。そのへんは主人に聞いたほうが早いかしらね。もっと年配の方じゃないと分からないかな。割と戦後すぐからじゃないかしらね。
現在の月島観音様入り口(三番街)
Q:相生橋を渡ったり、渡船に乗って大勢の方がやって来たと、聞いていますが。
そう、結構向こうから船で月島に来たって聞いてますよ。だから意外とそういうのは、戦後割と早くからやったと思いますよ。
Q:最近は縮小されて寂しくなりましたね。
ほんと、あれがなくなり、これがなくなりってね。参加する人が少ないから。
ということは、人が少ないから、やっていけないんじゃないかな。
Q:現在のことについてお尋ねします。ご自身のことも含めて、生活とかご近所とのおつきあいとか。
今、時代の流れでしょうがない。もんじゃ屋さんも増えて、もんじゃ屋さんばっかしになって、それぞれみんながんばってるから。横浜の中華街じゃないけどね。それはそれで町が成り立っているわけだから。
ー路地、路地に、買って楽しめるようなお店があるといい
あともう少し路地・路地に、買って楽しめるようなお店があると、将来いいかなって私は思うのね。もんじゃ屋さんだけじゃなくて、ちょっと買い物もできて、そういうお店もあったほうが、もっと人が来るんじゃないかなと私は思うの。
ー碁盤の目のような路地を利用して、もんじゃオンリーじゃなく
もんじゃ屋さんだけじゃなくてね。ちょうど碁盤の目みたくなっているから、路地・路地を利用して、そういうところに、いろんな楽しむ、買い物ができたり、そういうものができると月島もいいんじゃないかなと私は思います。もんじゃオンリーだけじゃなくてね。っていうのが、将来はね、私はそうなってもらいたいと思いますね。
Q:月島のことをあまり知らないでマンションに住む人に、月島ってこういうところだったというところをお伝えしたいですね。
どんどん古いところが壊されていっているから。なんていったらいいか、価値観っていうか、全然違う感覚で若い方は見てらっしゃるだろうから。
ーちょっと振り向くような街づくりを
すぐ銀座もあるし、足の便もいいですから。もっと昔のいいものを少しでも壊さずに戻し、ちょっと振り向くような感じでまちづくりをしていけば、外国からくるお客様もおいでになるだろうし、そういうので成功している町とか市があるでしょ。
だからそういうのを、ちょっと町の方が勉強して街づくりをちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。今のまんまじゃなくてね。絶対アイデアはあるから。
そうやっていかないと、ただもんじゃだけで埋もれてしまうとか、危機感はありますね。だから「あそこで食べたけど、あそこであれ売ってて」「あれもよかった」とか「楽しかった」とかいうものが同時にないと私はダメだと思う。
ー娘の時代、娘なんかも、「あれやった」「これやった」「楽しかった」って、クラス会で集まったりすると、皆さん、共通の思い出があるわけ。やっぱり同じことを言ってますよ。「浴衣着て楽しみだった」とかね、「あれ食べておいしかった」とかね、言ってますよ。「ああいうふうになればいいのにな」ってね。
今もう孫の世代ですけどね。孫たちにもああいうのを味あわせてあげたいなって思いますよね。それを多少経験しているのがうちの娘達ね。50代とか、40代後半とか。それ以降の若い方は、経験している方が少ないかなと思う。
Q:今度はお嬢さんたちの年代の方が思い出だけじゃなくて、残していってほしいですね。
私はたぶん一番いい時を経験して、今きてますから、ある意味、幸せだったなと思うのね。娘はそれをちょっとかじったくらいで、だから次の孫はあまりよく分からない。だから、娘もたまに、お母さんあれは楽しかったね、あれがよかったこうだね・・・ってちらっと言うんですよね。
孫とは話が違ってくる。思い出として話してあげるだけ。興味がないわけよね。こういうのを見せない限り分からないわけ。いくら言っても。
だからこういうのは孫のためにとってあるの。わたしがあれした後、孫にあげるために。
『中央区沿革図集[月島編]』
池本さんへのインタビュー 5/5 (インタビュアー宮本)
(2018.6.14)